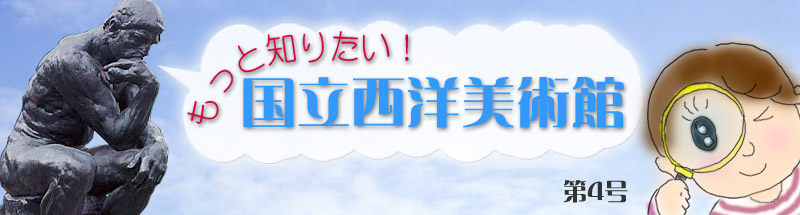|
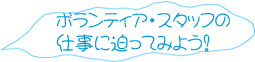 密着取材「スクール・ギャラリートーク」! 密着取材「スクール・ギャラリートーク」! |
 今回、取材したのはトレーニングを受けたボランティア・スタッフによる「スクール・ギャラリートーク」。事前に予約をした学校を対象に行われるプログラムです。ボランティア・スタッフの導入が始まって以来、ずっと続けてきたもっとも重要な仕事の一つだそうです。 今回、取材したのはトレーニングを受けたボランティア・スタッフによる「スクール・ギャラリートーク」。事前に予約をした学校を対象に行われるプログラムです。ボランティア・スタッフの導入が始まって以来、ずっと続けてきたもっとも重要な仕事の一つだそうです。
この日も中学校の美術部の生徒さんたちがやってきました。
挨拶をして、鑑賞のルール(騒がない・触らない・走らない)を確認すると、早速5〜6人のグループに分かれて「スクール・ギャラリートーク」がはじまります。
 いざ「スクール・ギャラリートーク」へ出発! いざ「スクール・ギャラリートーク」へ出発!
スクール・ギャラリートークでは常設展の作品3〜4点をグループに分かれて鑑賞します。
取材したグループが最初に鑑賞したのは彫刻、ジャン=バティスト・カルポー《ナポリの漁師の少年》。すっかりボランティア・スタッフに作品解説をしてもらえるものと思っていたらしい子どもたち。しかし、ボランティア・スタッフの第一声は「この作品を見て、どう思った?」でした。この言葉の投げかけに、解説を聞くだけと思っていた子どもたちはちょっとビックリした様子。
 “待つ”ことの大切さ “待つ”ことの大切さ
西美のスクール・ギャラリートークには一つの鉄則があります。
それは、「子どもの言葉を引き出すこと」つまりボランティア・スタッフが一方的に解説をするのではなく、作品を鑑賞した子どもひとりひとりが感じたことを、言葉にするのを“待つ”ことが、大事なひとつの役割であり、西美のスクール・ギャラリートークの特性になっているのです。
最初はとまどっていた子どもたちですが、「少年が楽しそう」「よく見ると貝や身体の線まで丁寧に作られている」など、自分の見た感想を次々に話し始めました。
絵画作品についても同様です。次に鑑賞したのは、エドワールト・コリール《ヴァニタス―書物と髑髏のある静物》。髑髏や火の消えた蝋燭、砂時計など「死」を連想させるような絵です。子どもたちにも「暗い絵」「骸骨があって気味が悪い」など、あまり評判は良くない様子。ボランティア・スタッフは「この絵は当時お金持ちのお家に飾られていました。あなただったらこの絵を自分の家に飾りたいと思う?」と尋ねました。答えは全員NOです。そこで、ボランティアはこの絵が描かれた時代背景を説明し始めました。「この絵は17世紀後半のオランダで描かれました。当時オランダは今でいうバブル絶頂の頃。多くの資本家が絵を買い求めましたが、彼らの間で流行ったのがこういった絵。贅沢をして怠けているといつか全てを失ってしまいますよと自分を戒めるために飾っていたのだそうです」。それを聞いた子どもたちは「自分の家には飾りたくないけど、絵の中のものが何を意味しているかわかったので面白い」と反応が180度変化している様でした。
 小道具でさらに興味津々 小道具でさらに興味津々
ボランティア・スタッフの工夫はまだまだあります。子どもたちから「まだ油絵具を使った経験が無い」と聞いたスタッフは、カバンから小さなカンヴァスに油絵具を塗ったものや、油絵の具用の絵筆、ペインティングナイフを取り出しました。これは西美の「びじゅつーる」という教材です。実際に道具に触ることで、子どもたちの油絵に対する興味はぐっと増していました。子どもの言葉に即座に対応して、小道具を出すところはまるで魔法使いのよう。さすがです。
40分ほど経って、スクールギャラリー・トークは終了です。最初は受動的だった子どもたちが徐々に色々な発言をするようになり、作品の見方が変わっていく様子が見られて同行していた私も一緒になって楽しんでしまいました。子どもたちが今後描く絵には、一体どのような変化が生じるでしょうか?ぜひ彼らの作品をみたいと感じました。
凝縮されたフィードバック
 ボランティア・スタッフの仕事はこの後も続きます。ボランティア室へ戻り、全員でこの日のスクール・ギャラリートークをフィードバックさせるわけです。このミーティングが実に面白い!短い時間の中に、担当した子どもたちや先生方の様子、こちらからの問いかけになかなか答えてくれない子に自分がどう対応したか、子どもたちの作品に対する反応などもきちんとすべて話されています。10分程度で無駄の無いペースで進んでいくこのミーティング、内容がぎゅっと濃くて聞いている私は大変勉強になりました。 ボランティア・スタッフの仕事はこの後も続きます。ボランティア室へ戻り、全員でこの日のスクール・ギャラリートークをフィードバックさせるわけです。このミーティングが実に面白い!短い時間の中に、担当した子どもたちや先生方の様子、こちらからの問いかけになかなか答えてくれない子に自分がどう対応したか、子どもたちの作品に対する反応などもきちんとすべて話されています。10分程度で無駄の無いペースで進んでいくこのミーティング、内容がぎゅっと濃くて聞いている私は大変勉強になりました。
「喋りたいのを我慢する」?
対象年齢もさまざまですし、ボランティア・スタッフは各々工夫してトークを組み立てていくのだそうです。その中で、一番苦労することは「喋りたいのを我慢する」ことだそうです。どうしても作品について知っていることを語りたくなるものですが、そこを堪えて、子どもたちが「どう思ったか、感じたか」を受けとめるのが重要な役割と言います。ご自身が子育てをされた経験のある方でも、子どもからの発言を“待つ”というのはとても難しいこと。「ボランティア・スタッフになって、“待つこと”を学びました。」と皆さんおっしゃっていました。また嬉しいのは子どもたちから質問があった時だそうです。子どもたちからの自発的な問いかけに喜びを感じるそうです。
そして「今、わたしたちがしていることが、子どもたちが大人になったとき、美術館を敷居の高いものと感じないで利用してくれるきっかけになってくれたら嬉しい」と話されていました。
現在、西美で活躍されているのは、なんとボランティア・スタッフ第1期生。今年5年目なのだそうです。初めはそれこそ試行錯誤で始まったそうですが、お話の仕方もスムーズで、子どもたちに「ヒント」となる言葉がけをするのも、とても上手。今では皆さんベテランです。スタッフは(たまたま)全員女性で、15名いらっしゃいます。
今年は新規のボランティアスタッフの募集もあるとのことなので(勿論男性の方でも大丈夫です)、ご興味のある方は、西美のサイトを要チェックですよ♪
http://www.nmwa.go.jp/
◆耳より情報◆
FUNDAYでボランティア・スタッフさんと会える!
西美で開催される無料イベント、FUNDAY(9月20日、21日)では、今年はボランティア・デスクが登場。ボランティア・スタッフについてより詳しく知りたい方は是非のぞいて見てはいかがでしょう。また、ボランティア・スタッフによる作品の前での10分間トークも企画されていますので参加してみてくださいね♪
西美FUNDAYのページはこちら
http://www.nmwa.go.jp/jp/events/fun-day.html |